「不妊治療中に引っ越しが決まったけど、助成金ってどうなるの?」
「新しい街の制度、何から調べればいいか分からない…」
こんにちは! 前回は、私が石川県から兵庫県へ引っ越した際の助成金制度の違いについてお話ししました。
今回は、さらに一歩踏み込んで、不妊治療中の引っ越しが治療や助成金申請に具体的にどんな影響を与えるのか、そして、知らずに損をしないための「落とし穴」と「賢い対策」について、私の体験も交えながら詳しく解説していきます!
転居を予定している方や、複数の自治体の制度を比較検討したい方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
引っ越しのタイミング、いつがベスト?実は超重要なんです!
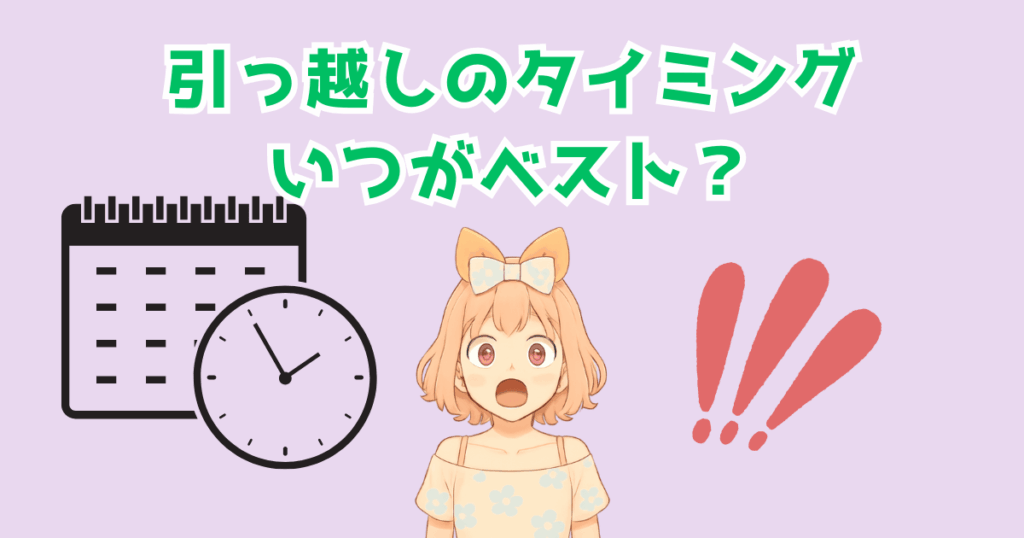
「いつ引っ越すか」って、不妊治療中だと本当に悩ましい問題ですよね。治療のステージや助成金の申請サイクルによって、ベストなタイミング、あるいは避けるべきタイミングがあるんです。
治療ステージとの兼ね合い:後悔しないために
採卵周期や移植周期の真っ只中での引っ越しは、できれば避けたいところ。
新しい病院探しや手続きでバタバタして、精神的にも身体的にも負担が大きくなりがちです。
理想は、一連の治療(例えば採卵~移植まで)が一区切りついたタイミングや、少し治療をお休みする期間。でも、そうもいかない場合もありますよね。そんな時は、まず今の担当医に相談してみましょう。
助成金の「年度」や「申請期限」も要チェック!
多くの自治体の助成金は、年度(4月~翌年3月など)で区切られていたり、治療終了後〇ヶ月以内といった申請期限が設けられています。
【落とし穴ポイント!】 引っ越し前に受けられる助成はしっかり申請しきるのが基本ですが、転居先の自治体で、引っ越し前の治療が助成対象になるケースも稀にあります(遡及適用など)。逆に、申請期限ギリギリで引っ越してしまい、旧住所の自治体への申請が間に合わなくなるなんてことも…。
【対策】 引っ越しが決まったら、まず両方の自治体の申請期限と条件を確認しましょう。
 ぶー奈
ぶー奈私の場合は、引っ越し前の自治体での助成回数を使い切ったタイミングでの引っ越しだったので、ある意味区切りは良かったです。
治療はどうなる?スムーズな移行のための確認ポイント
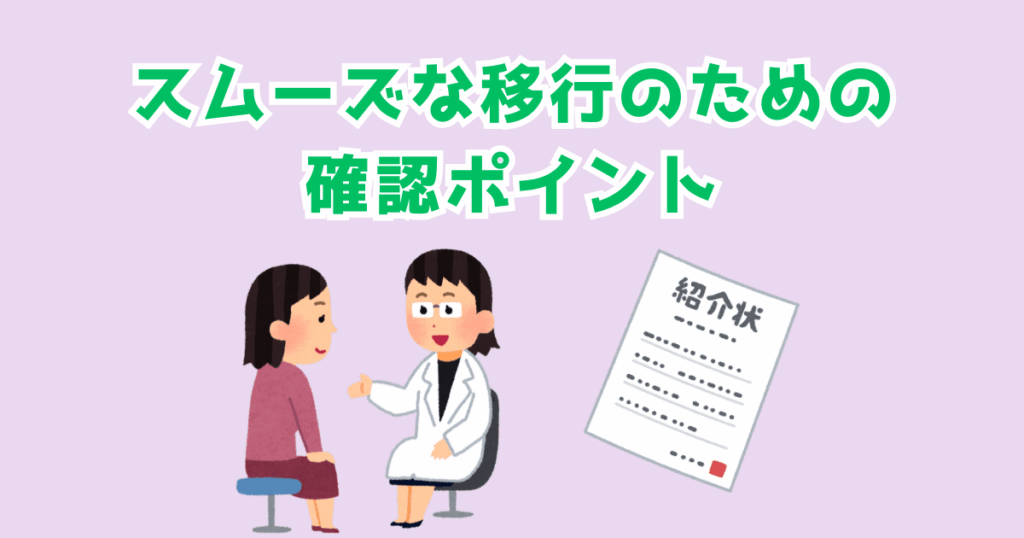
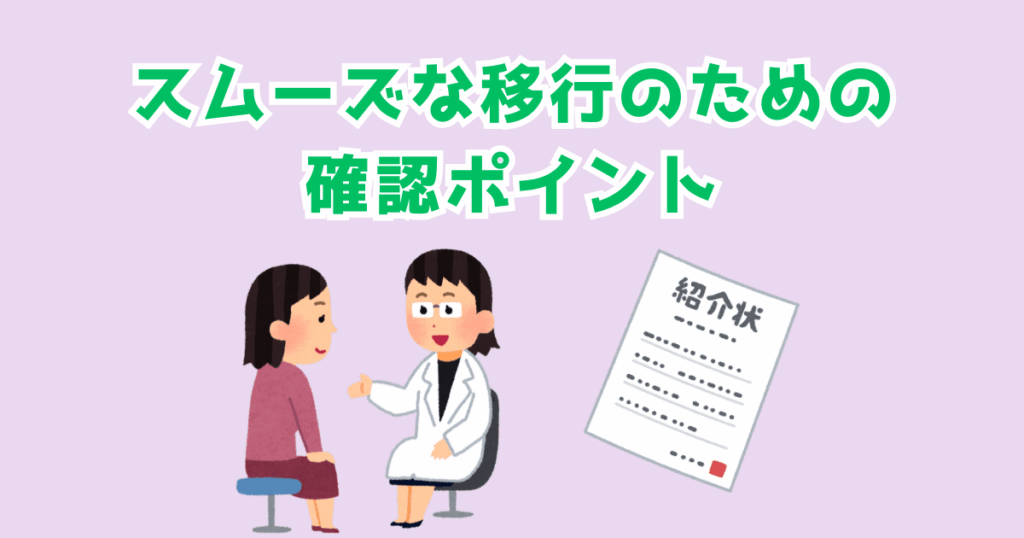
引っ越しとなると、一番心配なのは治療の継続ですよね。
病院探しと「紹介状」「治療データ」の重要性
引っ越し先でスムーズに治療を再開するためには、これまでの治療歴がわかる「紹介状(診療情報提供書)」と、検査結果や治療経過の記録が絶対に必要です。
これがないと、新しい病院で一から検査をやり直し…なんてことにもなりかねません。
【落とし穴ポイント!】 新しい病院が、転居先の自治体の「助成金指定医療機関」になっているかは必ず確認!せっかく良い病院を見つけても、指定医療機関でなければ助成が受けられない可能性があります。
【対策】 引っ越しが決まったら、今の病院に紹介状とデータ提供を依頼しつつ、転居先の指定医療機関をリストアップして早めにコンタクトを取りましょう。



転院前の先生はリストアップから転院先の病院について相談に乗ってくれました。
【最重要】助成金はどう変わる?転入時に絶対確認すべき「落とし穴」


さて、ここが一番デリケートで、かつ影響が大きい部分です。自治体によって制度が全く違うので油断は禁物!
「住民票の異動日」が運命の分かれ道?!
基本的に、不妊治療の助成金は、治療期間中に住民票があった自治体に申請することになります。住民票を移した日が、どちらの自治体の助成対象になるかの境目になることが多いです。
【落とし穴ポイント①】前自治体での治療は助成対象外になるケース
例:治療Aを旧住所で行い、治療終了前に新住所へ住民票を移動。新住所の自治体では「当市に住民票がある期間の治療のみ対象」という規定の場合、治療Aはどちらの自治体からも助成されない…なんて悲劇も。
【落とし穴ポイント②】治療回数のカウント方法
旧自治体で受けた助成回数が、新自治体でどう扱われるか(リセット?引き継ぎ?そもそもカウント方法が違う?)。これを知らないと「まだ助成してもらえると思っていたのに…」なんてことになりかねません。
【落とし穴ポイント③】所得制限・年齢制限・事実婚の扱いの違い
旧住所では対象だったのに、新住所では所得制限に引っかかったり、年齢制限を超えてしまったり、事実婚の証明方法が異なったりする場合があります。
【対策】転入時に役所で確認すべき最重要リスト!
- 私の住民票の異動日は〇月〇日です。この日をまたぐ治療(または引っ越し前に開始/終了した治療)は、どちらの自治体に申請すれば良いですか?
- 前住所の自治体で〇回の助成を受けていますが、貴市ではどのようにカウントされますか?(リセットされますか?通算されますか?)
- 貴市の助成金制度の所得制限、年齢制限、夫婦合算の所得で判断するかなどを教えてください。
- 事実婚の場合、必要な証明書類は何ですか?(パートナーシップ証明書でOK?住民票の続柄?など)
- 保険適用の治療は対象ですか?それとも保険適用外の治療のみですか?(←私の経験!)
- 先進医療や交通費の助成はありますか?上限額はいくらですか?
- 申請に必要な書類の一覧と、それぞれの書類の取得先、有効期限を教えてください。(特に所得証明書はいつの時点のものが必要か確認!)
- 申請期限は治療終了後いつまでですか?
- 指定医療機関のリストはありますか?
申請手続きも変わる!役所とのやり取り体験談と注意点
助成金の申請手続きも、引っ越しを挟むとちょっと複雑になります。
必要書類と申請方法の違い
治療証明書の様式が自治体ごとに異なる場合が多いです!旧住所の治療分は旧自治体の様式で、新住所の治療分は新自治体の様式で、それぞれ医療機関に作成してもらう必要があります。
役所とのやり取り、私の実体験と「こうすれば良かった!」
- 【注意点①:記録は命!】 電話で問い合わせた際は、必ず対応してくれた担当者の名前、日時、聞いた内容、回答をメモしておきましょう!後で「言った言わない」になるのを防げます。
- 【注意点②:質問リストは必須!】 聞きたいことを事前にリストアップしていくと、漏れがなくスムーズです。上記の「確認すべき最重要リスト」を参考にしてください。
- 【注意点③:ホームページの行間を読む】 自治体のホームページは情報が網羅されているようで、意外と細かい条件や「ただし書き」が見つけにくいことも。「よくある質問」や「申請の手引き(PDF)」なども隅々までチェック!
- 【注意点④:遠慮せずに聞く!】 少しでも「あれ?」と思ったら、遠慮せずに納得いくまで質問することが大切です。お金に関わる大事なことですから!
なぜこんなに違うの?自治体制度の統一化への願い
ここまで読んでいただいて、「なんで自治体によってこんなに制度が違うの?!」と思われた方も多いのではないでしょうか。私も本当にそう思います。
不妊治療は、どこに住んでいても同じように経済的・精神的な負担がかかるものです。それなのに、住んでいる場所によって受けられるサポートに大きな差があるのは、正直なところ不公平だと感じてしまいます。
治療のステージや経済状況に合わせて住む場所を選べるわけではありませんし、引っ越しによって治療の継続が困難になったり、受けられるはずだった助成が受けられなくなったりするのは、本当に辛いことです。
もちろん、各自治体で財政状況や優先課題が異なるのは理解できます。でも、せめて国の主導で、ある程度の基準や情報提供のフォーマットが統一されれば、私たち治療を受ける側の負担はかなり軽減されるのではないでしょうか。
安心して治療に専念できる環境が、全国どこでも整うことを心から願っています。
まとめ:不妊治療中の引っ越しは「情報収集」と「早めの行動」がカギ!
不妊治療中の引っ越しは、本当にいろいろな面に影響が出ます。でも、事前にしっかりと情報収集をして、計画的に動けば、治療への影響を最小限に抑え、受けられる助成をきちんと活用することができます。
一番大切なのは、引っ越しが決まったら、できるだけ早く、今の自治体と新しい自治体の両方の担当窓口に相談すること。
この記事が、少しでも皆さんの不安を軽くし、スムーズな引っ越しと治療継続のお役に立てれば嬉しいです!
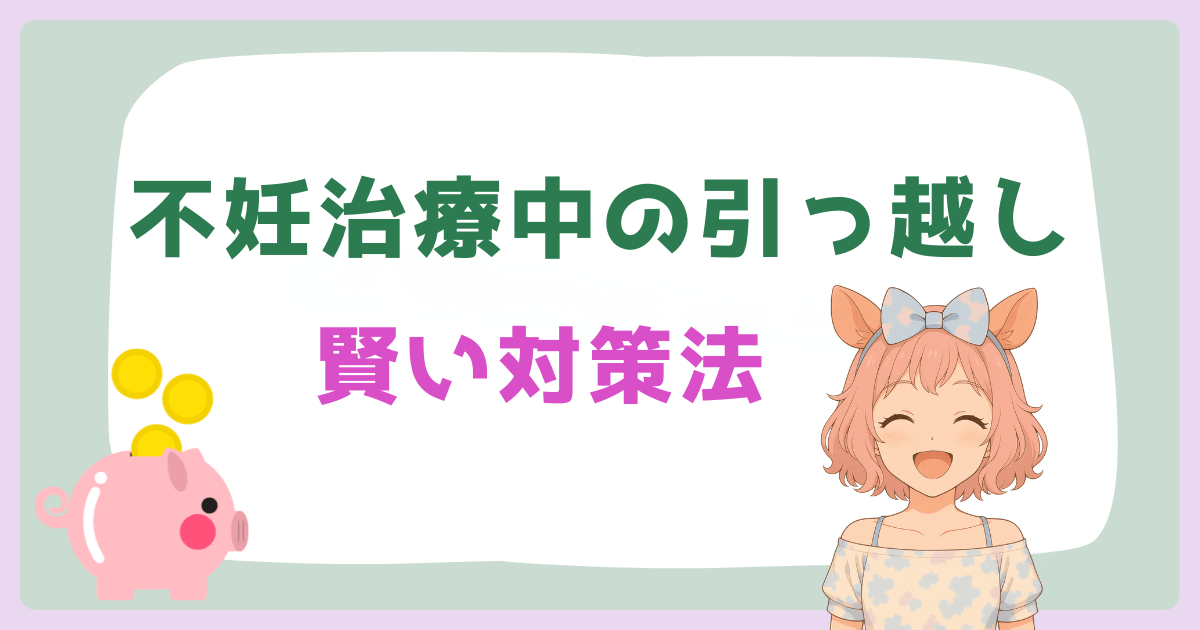
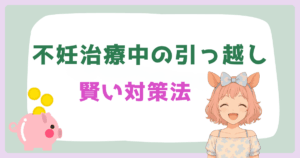
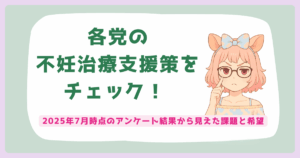
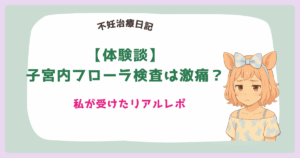
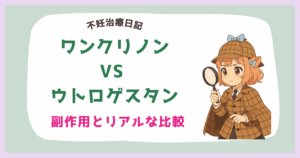
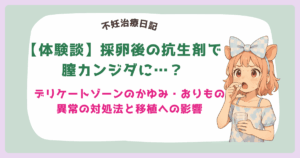
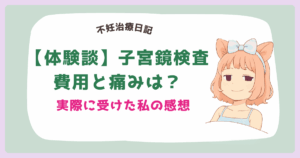
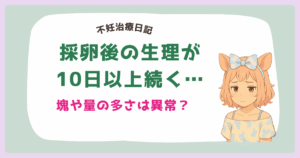
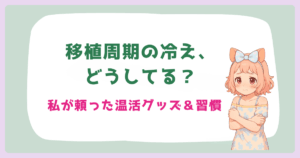
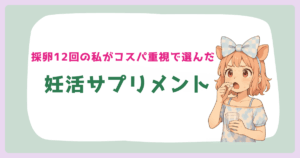
コメント